中国のモビリティ・物流イノベーション動向(2023年以降)
久しぶりの投稿となります。今回は中国におけるモビリティ・物流イノベーションにフォーカスを当ててみたいと思います。この領域は公共交通インフラの規制に係るため、国家の主導力がイノベーションの促進にとっては非常に重要になります。その意味でも中国は世界の最先端を走っています。2023年以降、中国のモビリティ(移動サービス)および物流分野では、テクノロジーを活用した革新的なビジネスモデルが次々と実用化されています。自動運転車や電気自動車(EV)、ドローン、人工知能(AI)などの技術を背景に、新サービスの商用展開と市場へのインパクトが顕著です。本ブログでは、主要な事例について企業名、サービス内容、採用技術、革新性、および導入効果や今後の展望を詳しく解説します。
自動運転ロボタクシーの商用展開

中国では複数の企業が都市部でロボタクシー(自動運転タクシー)の商用サービスを展開しています。
- Baidu(百度)Apollo Go – 中国検索大手の百度は、ここ数年で自社の自動運転タクシーサービス「Apollo Go」を北京、武漢、重慶などで展開し、2023年3月には北京市で完全無人運転の営業許可を取得しました。安全ドライバーも同乗しない完全無人のタクシー運行は、中国の都市で画期的なステップです。百度のロボタクシーは既に大規模に運用されており、2023年第4四半期だけで約83.9万回の乗車サービスを提供し、累計乗車回数は2024年10月時点で800万回を超えました。百度は第6世代の自動運転EV「Apollo RT6」を開発し、1台あたり20万元(約270万円)という低コストで大量生産が可能としています。これにより「ロボタクシーの乗車料金を将来的に人間のタクシーの半分に」することを目指すとされ、運営コストの劇的削減と2025年までの採算ライン到達(ユニットエコノミーでの黒字化)を見込んでいます。このように数千台規模の無人タクシーを都市に展開し、低価格で提供する計画は、市場に大きなインパクトを与えています。
- Pony.ai(小馬智行) – 自動運転スタートアップの雄であるPony.aiも百度と並んで実績を上げています。2023年3月に百度とともに北京で無人ロボタクシーの営業許可を取得し、その後も広州や深圳などでサービスを拡大しました。2024年7月には上海市でも無人運転の実証許可を得ており、現在では北京・上海・広州・深圳という中国4大都市すべてで完全無人の乗客サービスを展開するに至っています。Pony.aiはトヨタ製ミニバン(シエナ)をベースにした第6世代ロボタクシー車両を投入し、タクシー会社(例:上海の錦江タクシー)との提携でサービス区域を拡大しています。このような大都市圏への同時展開スピードは、中国当局の積極的な規制緩和と相まって、世界でも類を見ない規模です。市場インパクトとして、都市生活者がアプリで無人タクシーを日常的に呼べる環境が整いつつあり、移動サービスの形態を変革しています。
これらロボタクシーの革新性は、自動運転(レベル4)の高度技術を商用ライドシェアに組み込み、人件費ゼロの移動サービスを実現した点にあります。AIによる走行最適化やセンサー融合技術(LiDAR・カメラ・レーダー)により安全走行を図りつつ、ユーザーはスマホアプリで配車から決済まで完結します。導入効果として、既に百度Apollo Goは2023年通年で数百万件の実乗車を提供し、市民の移動ニーズに応えています。今後はサービスエリアのさらなる拡大と、採算性の向上(百度は2025年に単体黒字化予測)が見込まれ、将来的には公共交通を補完・代替しうる存在として期待されています。
自動運転バス・シャトルサービスの実証

ロボタクシーに加え、中国では自動運転技術をバスやシャトルといった公共交通にも応用しています。特に目立つのが広州発のスタートアップWeRide(文遠知行)による取り組みです。同社は2023年、広州市の公交集団(バス会社)と提携して中国初の有料自動運転ミニバス路線を開設しました。このミニバスは決められたルートを無人で走行し、専用レーンでのBRT(バス高速輸送システム)運行や深夜時間帯の路線も含まれています。乗客は通常のバス同様に利用でき、運賃収受も実施されています。
技術面では、WeRideのレベル4自動運転システムを小型バスに搭載し、車両にはLiDARやカメラが装備されています。固定ルートとはいえ都市部の交通混雑環境下で運行するため高度な認知・制御が必要ですが、同社は既に広州でロボタクシー運行の実績もあり、その延長で公共交通へ展開した形です。革新性は、公共輸送機関としての自動運転車両の商用運行を世界に先駆けて実現した点にあります。これはドライバー不足の解消策や、夜間・早朝など人件費が課題となる時間帯のサービス提供にも有効です。
導入効果として、WeRideのミニバス運行は乗客からの受容性を検証する良い機会となり、技術的にも安全に運行できることを示しました。加えて、中国国内で初めて自動運転バス専用のBRT路線を開通させたことは業界のマイルストーンです。今後の展望として、WeRideは2024年に無人配送バン(ロボバン)の公道テスト許可も取得するなど、乗客輸送以外の分野へも自動運転技術を広げています。各都市でも、空港内シャトルや産業団地内の自動運転バス実証が進んでおり、中国のスマートシティ戦略の一環として自動運転公共交通が拡充していく見通しです。
EVバッテリー交換サービスと電動物流の新モデル
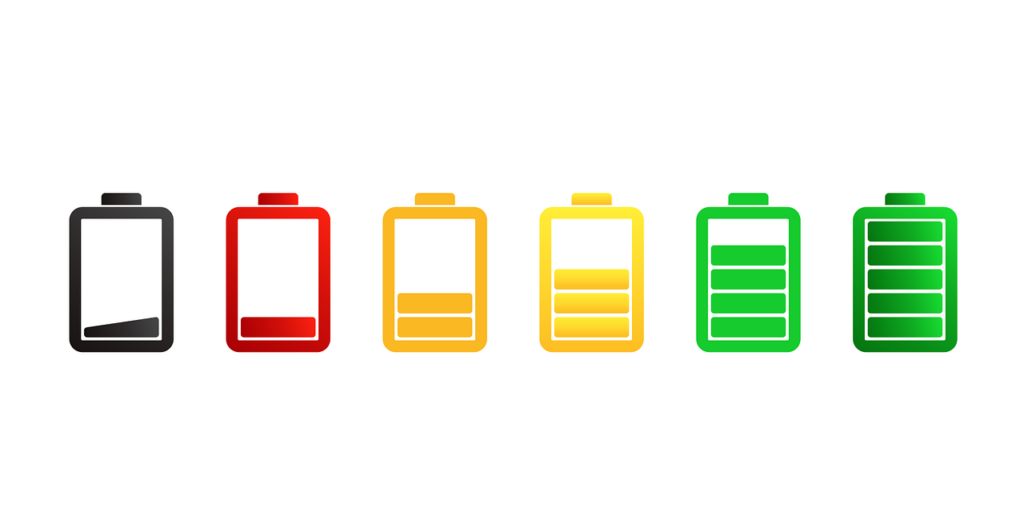
中国のEV普及を支える革新的モデルとして、バッテリー交換(バッテリースワップ)サービスが急速に拡大しています。バッテリー交換は、従来の充電スタンドでの充電に代わり、数分で空のバッテリーを満充電済みのものと交換する仕組みです。特に商用モビリティ(タクシーや運輸車両)での稼働率向上に寄与するとして注目されています。
- NIO(蔚来汽車)のBaaSモデル – 中国EVメーカーのNIOは、バッテリーを車体と切り離してサービス化する「Battery as a Service」モデルを先駆けて導入しました。2024年6月時点で中国国内に2,432カ所のバッテリー交換ステーションを設置しており、高速道路SAを含む広域ネットワークを構築しています。NIOオーナーは専用ステーションに車を乗り入れると、自動でバッテリーが交換され、約5分程度で再出発可能です。このモデルの革新性は、ユーザーがEV本体のみ購入しバッテリーは月額サービス契約にできる点で、高価なバッテリー所有コストを軽減しつつ充電待ち時間の問題も解決しました。またバッテリー標準化と劣化管理がサービス提供側で可能になるため、常に良好な性能の電池を利用できるメリットもあります。
- Geely系やBAIC系の参入 – 中国大手自動車メーカーもこの流れに加わっており、Geely(吉利)は自社のモビリティサービス「曹操出行(Caocao)」で交換式EVタクシーを運用開始、またBAIC(北汽)はAulton(奥動)新能源という交換技術企業と協力し、主にタクシー・ライドヘイル向けに交換ステーション網を構築中です。政府もEVタクシーへの交換ステーション導入を補助する施策を展開しており、北京市などではガソリンスタンド跡地にタクシー用交換ステーションが設置される例もあります。数分でエネルギー補給が完了するためタクシー稼働率が飛躍的に向上し、同じ車両で一日にこなせる乗車回数が増える効果が期待されています。
- CATL系「琪跡(Qiji)能源」による大型車両への応用 – 世界最大の電池メーカーCATL(寧徳時代)は、乗用車のみならず電気トラック向けのバッテリー交換にも乗り出しています。2023年8月には中国初の電動大型トラック用交換式サービス幹線となる寧徳~厦門間の高速道路幹線に交換ステーションを開通させました。さらに2024年11月には深圳の盐田港にて世界初の港湾内大型トラック交換ステーションを稼働開始しています。港湾では100台近い電動コンテナ輸送トラックが配備され、交換ステーションでの電池交換により従来1時間の充電を5分程度に短縮し、港のオペレーション効率を大きく高めています。CATL子会社の琪跡能源が開発した底部交換式バッテリー(342kWh)は、トラック下部から電池を抜き差しする設計で、車両の重心安定や大型電池搭載を両立しています。導入効果として、第一陣の約100台の電動トラック稼働で年間5,000トン超のCO2削減見込みや、燃料コスト20%低減といった成果が報告されています。
このように、中国は世界最大規模のバッテリー交換インフラを構築しつつあり、政府目標では2025年までに全国で1.6万カ所超の換電ステーション設置が掲げられています。革新性は、EVの弱点だった充電時間とバッテリーコスト問題をビジネスモデルの工夫で克服した点です。市場インパクトも大きく、NIOは交換サービスを武器にユーザー基盤を拡大し、CATLは石油会社(中石化など)と提携してガソリンスタンドを交換ステーション化する計画も進めています。今後の展望として、交換式EVはタクシー・物流から民間乗用車へと広がる可能性があり、中国発のこのモデルが世界各国にも波及することが期待されます。
ドローンによる無人配送サービス

都市上空を飛行し配送を行うMeituanのドローン(ドバイでの実証飛行)。中国では、ラストマイル配送の自動化にもドローン(無人航空機)が活躍し始めています。なかでも美団(Meituan)は、オンデマンドデリバリー(フードデリバリー)の分野でドローン配送を本格展開している先駆者です。
- Meituanのドローン宅配網 – Meituanは2017年にドローン配送プロジェクトを開始し、2022年頃から深圳市内で実用サービスを開始しました。2025年4月には中国民用航空局(CAAC)より全国範囲での低空物流運航資格(営業許可)を国内で初めて取得しており、技術面・安全面での実績が国に認められた形です。同社の自社開発した第4世代ドローンは-20℃~50℃の気温や中雨・降雪、風速10m/s程度の風にも耐え、夜間飛行も可能とされています。こうした耐候性に優れる機体を多数投入し、2024年末までに延べ45万回以上の商業配送フライトを達成、深圳・北京・上海・南京など中国各地で53の定常ルートを運用しました。配送先はオフィスビルや大学キャンパス、公園内受取ステーションなど多岐にわたり、都市部における新たな配送手段として定着しつつあります。
- ビジネスモデルと革新性 – Meituanのドローン配送は、注文から受取までを自社プラットフォームでシームレスに提供します。ユーザーがスマホアプリで食事や商品を注文すると、近隣のドローン拠点からドローンが発進し、目的地近くの受取ボックスまで荷物を空輸します。受取ボックスではドローンが上部から荷物を投下し、利用者はパスコード等でボックスを開けて品物を取得する仕組みです。このモデルの革新性は、地上配達員では困難な高速配送を可能にした点です。都市の渋滞や河川・公園等の障害を上空経路で迂回でき、平均20分程度で注文品が届く様子は「未来的な光景だが中国では次第に日常になりつつある」と報じられています。人手不足や配達員の労働負担増が課題となる中、無人機で補完するこの手法は効率化とサービス水準向上の両面で意義があります。
- 導入効果と展望 – Meituanの実績はGoogle傘下のWingと並び世界トップクラスのドローン物流規模と評価されており、商用配送数で両社が肩を並べていると報じられました。利用者からは配送の迅速さが好評で、オフィス街などではランチタイムの新たな選択肢となっています。Meituan自身も**「今後3~5年でドローン配送コストを地上配達と遜色ないレベルまで下げられる」と見込んでおり、スケール拡大による効率向上に自信を示しています。同社は2025年に入り、香港でのドローン配送サービス開始や、中東ドバイへの進出(海外ブランド「Keeta」名義)など海外展開も加速**しています。中国国内では政府が「低空経済」振興政策を打ち出し、各地で都市低空域のルール整備が進んでいるため、Meituan以外にもSFエクスプレス(順豊)やJD物流(京東)など大手が無人機物流に参入中です。今後、都市部の即時配送や山間部・離島への物資輸送など、ドローンが物流の重要インフラとして定着していく展望が開けています。
スマート倉庫とAIによる物流効率化

完全自動化された上海の物流センター内部(Cainiao提供)。EC(電子商取引)大国の中国では、物流倉庫の自動化・知能化にも最先端技術が投入されています。Alibaba(阿里巴巴)グループの物流子会社Cainiao(菜鳥)は、その代表例であり、近年「スマート倉庫」を各地に展開しています。
- Hema鮮生(盒馬)上海物流センターの事例 – 2023年7月、Alibaba系列の生鮮スーパーHema向けに上海市郊外で稼働開始した供給センターは、Cainiaoの技術で従来にないフルオートメーション化を実現しました。延床数万㎡規模の倉庫内には200台ものAGV(自動搬送ロボット)が走り回り、商品を載せた青いコンテナ箱をピッキングステーションへ自動搬送します。これにより作業者は歩き回る必要がなくなり、従来1日1万~2万歩も商品棚間を移動していたピッキング作業が劇的に効率化されました。Cainiao担当者は「人が商品を探す作業から、商品が人を探しに来る方式へ転換した」と述べています。また、仕分けには高速なクロスベルトソーター、荷降ろしにはロボットアームも導入され、倉庫全体を統括するWCS(倉庫制御システム)とAI最適化アルゴリズムが数百台規模の機器を協調制御しています。CainiaoのWCSは20種類以上の異なる自動化設備を統合制御し、1倉庫で最大1000台超のAGVを同時に捌く能力を持つとされます。AIによるタスク最適化や経路計画により、人・ロボット・在庫の三者が滑らかに連携する「スマート倉庫」を実現しています。
- 効果と革新性 – こうした自動化物流センターでは、日次処理能力が飛躍的に向上します。実際、上海のHema供給センターでは1日あたり280万件以上の注文仕分けを処理可能となり、Hema店舗やEC顧客への配送リードタイム短縮に貢献しています。精度も人手より高く、在庫データとリアルタイム連動することで欠品やミスを低減しました。労働環境面でも、重労働や単純作業が機械に代替されることで従業員の負担軽減・効率的配置が可能となっています。革新性は、IoTや5G、クラウドコンピューティングを駆使して物流プロセス全体をデジタル化・自動化した点です。従来はサイロ化していた様々な機器を統合制御し、大規模ロボット群を“見える化”された一つのシステムとして運用するアプローチは、中国の巨大EC物流を下支えする新たな基盤技術と言えます。
- 普及と展望 – Cainiaoは自社グループ内のみならず、この倉庫ソリューションを外部企業にも提供し始めており、国内外での導入事例を増やしています。中国内では他にJD.com(京東)も「Asia No.1」と呼ばれる高度自動倉庫網を運営するなど、主要物流企業が競ってAI・ロボティクスを物流に投入しています。今後は、需要予測AIと連動した在庫最適化や、**ロボット技術の更なる進化(ピッキングロボットの高性能化等)**が進み、完全無人倉庫の実現に近づくでしょう。また、これらスマート物流技術は海外市場からの関心も高く、Cainiaoはヨーロッパの展示会でRFID自動認識やスマートパーク(物流園区)管理技術を披露するなど、中国発の物流テクノロジーが世界のサプライチェーンを変革しうるポテンシャルを示しています。
自動運転トラックによる長距離物流効率化

人の移動や倉庫内作業だけでなく、長距離物流(トラック輸送)分野でもAI自動運転技術の活用が進んでいます。中国は広大な国土をカバーするトラック網が年間4兆元(約55兆円)規模とも言われますが、ドライバー不足やコスト高が課題です。こうした中、スタートアップ各社が自動運転トラック(商用車)の実用化に挑んでいます。
- Inceptio Technology(仙途智能) – 上海拠点のInceptioは、レベル3相当の「ドライバーアシスト自動運転」技術をトラックに搭載し、既に商用運行で大きな実績を上げています。同社は東風汽車などのメーカーと提携し、独自開発の自動運転システムを工場出荷時に組み込んだ量産トラックを販売するモデルを取っています。2023年時点で約600台のInceptio搭載トラックが中国各地の物流企業により運行されており、2024年半ばまでにその数を4倍(約2400台)に増やす計画です。導入企業はネスレやバドワイザーといったグローバル荷主から、中通貨運・德邦物流といった中国大手物流会社まで多岐にわたり、長距離輸送の効率化手段として期待されています。同社システムは、高速道路のような長距離区間であれば人間ドライバー1名で従来2名必要だった行程を走破でき、輸送コストを5~7%削減できるとされています。実際、Inceptio搭載トラックは2022年に商用運行累計1億kmを無事故で達成しており(2023年には2億km超)と報じられるなど、安全かつ安定した運用実績を積み重ねています。
- 技術的特徴と革新性 – Inceptioのアプローチは、完全無人運転(レベル4/5)に一足飛びするのではなく、現行の法規で許容されるドライバー付き自動運転(レベル3)でまず商用価値を創出している点に特徴があります。AIと各種センサーにより、車線維持・前車追従・自動緊急ブレーキなど高度運転支援を行い、ドライバーの疲労を軽減しつつ効率的な走行を実現します。ドライバーは休憩や交代の頻度を減らせるため輸送時間を短縮でき、結果として物流会社のコスト削減やサービス向上につながります。革新性は、自動運転トラック産業のサプライチェーンを中国国内でまとめ上げた点にもあります。InceptioのCEOは「チップ・センサー・車両メーカー・AIデベロッパーが一体となったエコシステム構築において、中国は世界をリードしている」と述べており、自社も含め今後数年で2~3社の「ロボトラック」専業企業が台頭するとの見通しを示しています。
- 導入効果と今後 – 現時点でInceptioのシステムは人手不足が深刻な長距離トラック輸送の生産性向上に寄与しています。大手物流企業にとって5~7%のコスト削減は競争力強化に直結し、市場からの需要も高まっています。また同社は将来的に車両販売だけでなくソフトウェアによる車隊管理サービス提供にも乗り出す計画で、ビジネスモデルの幅を広げています。他にも、先述のWeRideは2024年に中国初の無人運転配送バンのテスト許可を取得し実証を開始しており、都市内配送でも自動運転の活用が進みつつあります。法規制の面では完全無人の公道長距離運転はまだ認められていませんが、中国政府はエリア限定のパイロットプログラム等で技術検証を支援しています。今後規制が整えば、人間ドライバー不在のトラック車隊による24時間稼働も視野に入り、物流の生産性は飛躍的に高まるでしょう。
おわりに:革新がもたらす未来展望

以上のように、2023年以降の中国におけるモビリティ・物流分野は、自動運転技術を核とした移動サービスの革新、電動化とインフラ整備による新ビジネスモデルの確立、そしてAI・ロボティクス活用による効率化が同時並行で進んでいます。これらの事例はいずれも技術革新とビジネスモデル創出が相まって社会実装を達成している点に特徴があります。政府による規制緩和・支援(例:ロボタクシー特区の設置や低空経済圏の整備)が後押しし、民間企業の大胆な実証とスケール戦略が功を奏しています。
中国市場で生まれたモビリティ・物流の新モデルは、そのスピード感とスケールで世界にも影響を与え始めています。例えば、百度やPony.aiのロボタクシー成功は各国の自動運転実用化を刺激し、NIOのバッテリー交換モデルは欧州でもサービス提供が検討されています。Meituanのドローン配送やCainiaoのスマート物流技術も海外へ展開が進み、中国発イノベーションがグローバル標準となる可能性も出てきました。今後は、これら先進事例から得られたデータと経験をもとに、さらなるサービス改善や新ビジネスの派生が期待されます。モビリティと物流の融合、例えば自動運転車による移動販売や、ドローンとロボットを組み合わせたシームレス配送など、次なる展開も視野に入ります。中国は引き続き実証と改善を重ねながら、モビリティ・物流の未来像を塗り替えていくでしょう。
◇GlobeNexusのスポットコンサルティングで海外進出の不安を解消
海外進出を成功させるには、現地のリアルな情報をいかに素早く、正確につかめるかが鍵です。スポットコンサルティングを活用すれば、無駄な遠回りをせず、成長市場への一歩を確実に踏み出せます。
GlobeNexusでは、海外進出に挑む企業を対象に、スポットコンサルティングサービス(セカイズカン)を提供しています。市場調査・販路開拓・現地パートナー探しなど、貴社の課題に応じた専門家がサポートします。まずはお気軽にご相談ください。


